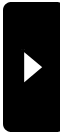子どもの権利条例ができるって!」のワークショップには、なんと60人もの方々が参加
2月2日の「みんな集まれ!長野市に子どもの権利条例ができるって!」のワークショップには、なんと60人もの方々が参加して下さいました。もともと「つくりましょう!!」と言い出したわけではなく、いつのまにか?「もう作ってます!!」という状況でしたので、そのショックというか、ワクワク感などを共有したくて開催したワークショップです。それにしても、24人しか座れない会場を予約していた私は、日に日にお問い合わせが増えるので「もしや?」と思い、たまたま空いていた「ホール」に予約を変更したら正解でした。(これだけでヒヤヒヤドキドキ)
「長野市はどうして急に条例を作ろうと言い出したの?」とか「誰がどんなふうにどんな条例にしようとしているの?」「議会ではどんな議論が始まっているの?」など、素朴な疑問にお答えいただくために、長野市子ども政策課の方を「出前講座」でお招きし、お話しいただきました。お願いした時に「途上のことなので、細かいことや質問や意見にはお答えできかねます」と言われておりました。無論、私たちが勝手に開いているワークショップであり、市が「市民の意見を聞くために」開催しているワークショップでは無いので、そこは質問・発言はなし。というお約束で、報告が済み次第、お帰りいただきました。
そのあと、「なんで質問に答えない!」と、お怒りの声もありましたが、参加者もどちらかと言えば言いにくいこと(証拠の無い憶測とか)もどんどん発言できて、良かったかな?と思います。
長野子どもにやさしいまちフォーラムからは、すでに「この条例にオンブズパーソンの制定を」という署名が準備されていましたから、ここは「総合条例としての肝」ともいわれるものなので、たぶん?想定されていない条例案に横やりを入れられるのはつらかったろうと思います。
この件をより明確にするために、条例のある松本市から、人権擁護委員の北川弁護士をお招きし、条例のある松本市の相談・支援・救済のしくみや実情をご報告いただきました。「保育園が日陰になるので、建設予定者に変更を依頼した」という事例では、「青木島公園も条例があれば子どもの権利をどう保障するのかを考えられるね」と納得。条例は市や施設・民間のあらゆる子どもの居場所で「守られなければいけない約束」なので、「やれることはやっています」では終わらないで「子どもの最善の利益」を守ります。もちろん、市民全体の意識やそれを実行しようとする人を議会に送る投票行動にも影響があります。
「子どもの権利条例を作りました」という看板を掲げるだけでなく、条例を実効性あるものにする決意を持った人に、市政を任せたいと思います。
子どもの権利条約31条推しの小林としては、ぜひこの条約の理念のすばらしさを共有したいと思ってワークショップを開催しています。「子どものしあわせな時間」が、何にもとらわれない自由な時間であることを私たちはもっと思い出したいです。(国連子どもの権利委員会からも忠告されている)
「子どもの経験」を3万円のカードでプレゼントする前に、子どもが自由にのびやかに過ごせる空間と時間と見守りの大人をプレゼントして欲しい。
さて、ということで、この条例の行方を見守りつつ、「市政」には厳しい目を「子どもの権利」に照らして向けていきたいですね。
次回には、案外むずかしい「子どもの権利条約」の理解と学習を、主権者である「子ども」目線でワークショップしてみたいと思います。3月30日。高校会館。