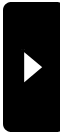長野の子ども白書掲載予定記事紹介 ⑫社会的養護の担い手としての里親とこどもの権利
社会的養護の担い手としての里親とこどもの権利
中信地区里親会 牟禮 孝貴
こども家庭庁が発足し、こども基本法の目的が「児童の権利に関する条約(以下「条約」)」の精神にのっとり、その権利の擁護が図られ」とされ、基本理念にも子どもの権利が明記されるなど「こどもまんなか社会」へのスタートがきられました。
一方で社会的養護の一部を担う養育里親の処遇については、まだまだ不十分な面もあります。令和5年10月には地方紙で「里親トラブル 立場弱く」の見出しで、行政側が一時保護に至った理由を里親に十分に示さず、突然里子と引き離された里親とトラブルになっている事例が県内外で数多くおきているという報道がなされたところです。こどもの権利を尊重した里子の養育とそれを担保するための里親支援、里親に求められる権利について現状と課題を考えてみたいと思います。
1 養育里親とは
実親の病気など何らかの事情により家庭での養育が困難又は受けられないこどもを自らの家庭に迎え入れ、一時的に養育するのが里親です。里親家庭での生活を通じて、自己の存在を受け入れられているという安心感の中で、特定の大人との愛着関係を作りながらこどもの健全な育成を図る制度です。(条約第20条)里親は、親と離れて暮らす子どもの養育を担い、児童相談所はその里親・里子を支援すし、「こどもの最善の利益」(条約第3条)を目指すという協働関係にあると言えます。
2 里親養育におけるこどもの権利
(1)長野県の家庭養育の現状
令和4年度末の里親等委託率は19.6%にとどまっており、約8割の子どもは依然として施設での養育になっています。家庭養育を増やすためには里親制度への理解を深め、実親の同意を得やすくする。受け皿となる里親の数を増やしていくなどの課題があります。
(2)生きる権利、育つ権利、守られる権利(条約第6条)
里子のなかには食事が十分摂れていなかった、入浴していなかった、寝具で寝ていなかった等の厳しいケースもありますが、里親宅では、衣食住を確保した安全・安心な暮らしを提供し、こどものペースに合わせた暮らしを心がけています。国で決められている「里親が行う養育に関する最低基準」では、自主性の尊重、虐待や差別の禁止、教育、健康管理、衛生管理などが定められており、里親は、その最低基準を超えて、常に、その行う養育の内容を向上させるように努めることになっています。
(3)意見表明権(条約第12条)
こどもが自分に影響を与えるすべての事柄について自由に意見を表明する権利を保障すると同時に、こどもの意見がその年齢および成熟度にしたがって尊重されるとされています。(100%こどもの言いなりになる訳ではありませんが)
しかし、こどもは利害関係が強い人ほど本音は伝えにくいものです。正直に伝えると嫌われてしまうかも。一緒に暮らせなくなるかも。私ががまんすれば他の人を傷つけることにはならないかもなどの気持ちがあるからです。嫌なこと(虐待)をされていても言い出せないこともあるかもしれません。そこで、中立的な意見表明支援員がこどもの声を聞き、意見表明を援助することが求められています。現在、この「こどもアドボカシー」の仕組み作りが進行中です。里親家庭でもこどもの意思を尊重するようにしています。例えば里親の呼び方を決めてもらう、寝る場所を選択してもらう(和室の座卓の下を選んだ里子もいました)、学校で実名を使うか通称名にするかなどです。
(4)こどもの最善の利益(条約第3条)
こどもに関係することを決めたり、行う時は、「その子にとって最もいいことは何か」を第一に考えるということです。児童相談所が措置決定する時はもちろん、里親家庭でも進学で特別支援学級、通級教室、通常のうちどの学級がいいのか。お手伝いしてもらうかどうか又その内容は。食事の内容は。ペット飼うかどうかなど様々な場面で考慮する必要があります。その際は2(3)のこどもの意見を聴き、尊重することも必要になります。
3 養育里親への支援と里親の権利
(1)里親支援機関(フォスタリング業務)について
児童相談所、民間のフォスタリング機関(令和6年4月から「里親支援センター」)が里親支援を包括的に行っています。その内容は・里親制度等普及促進・リクルート業務、・里親研修・トレーニング等業務、・里親委託推進等業務、・里親訪問等支援業務、・里親等委託児童自立支援業務などです。
(2)里親訪問等支援業務
この業務は、里親不調を防ぎ、安定した養育を継続できるように様々な支援を行います。支援には未委託期間中及び委託解除後のフォローも含まれます。通常の相談業務や里親同士のつながりを深める里親サロンの開催に加え、相談員が定期的に里親宅を訪問し、里親や里子から生活の様子等を聞き取ります。家庭訪問は、里親にとって、悩みを相談したり、普段の養育をふり返る貴重な機会にもなっています。
(3)里親支援の課題と里親の権利
受託する際に、里子の特性や成育歴などの情報が児童相談所から提供されない。自立支援計画の内容が十分でないなどの指摘があります。中途からの養育なので手探りでのスタートになるのは致し方ない面があるものの必要な情報は出してほしいという声や、相談時間は平日の日中に限られることが多いが、休日夜間に相談案件が発生することが多く、いつでも相談できる体制が望ましいとの声が出されています。
また、新聞報道のように里親と児童相談所の間で「こどもの最善の利益」をめぐって意見が異なるケースもみられます。意見が対立した時は里親側の立場が弱く、不本意だとしても措置解除を受け入れざるを得ません。
里親は親権を持っていませんが、一定期間親の代理として養育しており、里子のウエルビーイングの観点から措置変更に関する意見を表明し、尊重される権利が必要だと思われます。
(4)措置解除後のフォロー
措置解除は里親にとって喪失感を生みます。特に予定外の解除の場合はなおさらです。里親の喪失感についてのフォローが適切になされなければ、解除の決定を行った児童相談所との関係が不安定になり、次の里子の委託が滞ることもあります。
また、措置解除によって里子とは他人(知人)の関係になり、現状ではその後の暮らしを知る権限がありません。里子が希望し、保護者が同意すれば解除後の交流を認める権利も必要だと思われます。今後の生活を応援しているよと伝える(会話や手紙)機会を設けることは里子にとっても大切だと思います。
前に述べたとおり、里親と児童相談所は「こどもの最善の利益」を目指すという協働関係にあります。普段から連携を密にし、信頼関係を構築し、里親トラブルを未然に防ぐ努力が双方に求められています。
<参考>里親家庭の「おわかれ」にかかわる3つの視角
三輪 清子(明治学院大学)福祉社会学研究 17から抜粋
里親自身からは、措置変更(実親との交流開始のため児童養護施設に措置変更されたが実家庭に長期間戻れていない事例)になった時のことが以下のように語られた。
F夫:これだけ里親認定前研修受けて、一生懸命資格を取って、やろうとしている人に対して.実際にやっていて「明日でおわかれね」という電話一本で言って、車来てビューと持っていくみたいな。涙ぽろぽろになるわけじゃないですか。三日三晩寝込むとか。
F妻:そう。縁を切られる。せっかくつながったのに、やっぱり切られてしまう。
里親からは措置変更によって、つながりが切断されることにより、大きな喪失感を抱えることが語られた。同時に「ではどんなことがあれば安心か」という問いに対しては、以下のように語られた。
F妻:私らは「元気にしていますよ」という一言でほっと安心する。もう喜んで、写真一枚でも親子の写真見せてもらったらすごいうれしいやろうし。うそをつかんと、正直に伝えてくれたら安心かな。
里親からは、喪失感は消えないかもしれないが、子どもが幸せに暮らしていることがわかれば、安心すると語られた。里親自身は、児相と里親の関係をどう捉えているのか。
F 妻:「私ら将棋の駒と一緒やな」と思うことがしょっちゅうあって.利用されているという言い方もおかしいねんけれども、あの人らと喋るとそういう風な感じに捉えてしまう。