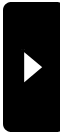2024長野の子ども白書掲載予定記事紹介 ③地域課題として「子どもの声から学校を考える対話の場」をつくりたい
地域課題として「子どもの声から学校を考える対話の場」をつくりたい
となりのチカラ 代表 西山 良子
3年前に親の会を始めて、不登校約30万人という現状に率直に思うことは、「この数字をいつまで子どもたちに背負わせるのだろう?」ということです。子ども・親・先生の努力、忍耐、根気に依存し、子どもの側を変えるだけの支援ではなく、「不登校」「学校に合わない子ども」の側に立って考え、学校そのものを改革していかなければ子どもが学校からいなくなる日も近いと思っています。「学校がいやだ!変だ!行きたくない!」という子どもの声を無視して学校の未来はないということを社会や地域の課題として捉え、大人から変えていく必要があると思っています。
なぜそんな風に考えるようになったのか?
私自身、小中学校は毎日行きたい場所ではありませんでしたが、学校なんてそんなもんだと我慢して通っていた記憶があります。
自分の感覚を無視して「そんなもんだと我慢する」ことが学校に通う間に板につき、社会に出てもいろんなことをあきらめて大人になった自覚があります。娘が小学生になり親として学校を見た時、40年以上前に記憶している小学校とほとんど変わっていなくて、それ以上に何だか窮屈で相変わらず我慢して行くような場所であることに、親になった私はチクリと胸が痛くなりました。なぜなら、何も変えようとせず変えることができるとも思わずに、我慢して、あきらめて、やり過ごしてきた結果、今の学校を子どもたちに残してしまったのだろうと思うからです。だから余計に、娘が学校から遠ざかることには、早いうちから納得しました。なので、「一緒にフリースクールを見に行こう」「学校じゃなくても学べる場所はたくさんあるから大丈夫」と、学校からさっさと遠ざかろうと提案したりもしましたが、娘は3年後、再び学校に行き始めました。むしろ「学校以外に行くつもりはない」とずっと言っていました。 そんな娘の思いは「学校に行けるなら行きたい」。そういう気持ちで休んでいる子どもは結構多いことを親の会を通しても感じました。もちろん、「学校に行くべき」という周囲の圧力もあるとは思いますが、それだけではなく、みんなが同じ地域で同じ場所に通い、同じ年齢で同じ学びを経験している。「強制的に6歳になったらここに毎日行くんだよ」と用意された場所。そんな風に大多数の同年代が通る、人生の一部に食い込んだ、まるで通過儀礼のような側面を持ち合わせるのが学校なのではないかと思うのです。みんなと同じようにできないことが後ろめたく、やるせなく思うことや、孤立感を抱いてしまうのは、その子の立場で想像してみれば当然のことで、単に学ぶ場を確保できればいいという話じゃないのも分かるかと思います。 親も通過儀礼を通らず、学校に行かない道を子どもと進んでいくうちに、運動会や修学旅行、テスト勉強や受験など、知らないままでいいんだろうか? (人と比べて)成長できないんじゃないか? 不安と心配が波のように押し寄せてきます。高校は中学と違って自由に選べると言うけれど、結局高校に行くなら学校生活を送れるのが前提で、それができなきゃ話にならないと中3受験期に突きつけられて、義務教育が終わる焦燥感に我を失って子どもを追い詰めてしまうことがあるのは、親も追い詰められているから。どこまでいっても世の中に合わせなきゃ生きていけない、子どもも親もレールから降りているようで完全には降りられずに、結局は、子どもが周囲に合わせられるよう教育していくという形に戻されてしまうように感じます。
学校のあるあるが子どもを苦しめる
中学から娘が再び学校に行こうと思ったきっかけは、友達との時間を取り戻したいという切実な思いからでした。3年間、家でつながりを断っていたことで、その時間の尊さを感じられたのかもしれません。ただ、不登校から再び学校への道は簡単ではないんです。学校自体は不登校前と何ら変わっていないので、元気になったら我慢ができるようになるものでも適合できるようになるものでもなく、むしろさらに嫌気がさして、疲れるし、先生は最悪だし、「やっぱり行きたくなくなる」となってしまう。非常に残念なことに、心身を健やかに保ち、自尊心を失わない生活を送るためには、「学校に行かない方がよっぽど娘の人生にとっていいんじゃないか?」ともやもやした気持ちになったりもします。不登校に関してはいろいろな調査が行われていますが、学校で当たり前になっていることが辛いと言う子どもが多くいます。その中でも先生からの関わり、体罰や暴言までいかないが「こんなことも分からないの?」「1回しか言わないって言ったでしょ(だからもう言わない)」「さっさと書け!」「どうせまた〇〇だろ」「もういい!」みたいな皮肉、嫌味、決めつけ、高圧的な態度です。これが本当に子どものこころを痛めつけるし、疲弊させる。家庭での子どもに対する不適切な関わりがマルトリーメントと言われますが、「教室マルトリートメント」という本もあり、学校では「指導」として認識されてしまうこともあるのです。しかも、当たり前の光景でそのことに誰も声を上げないし、上げたところで何も変わらないし、説教されるだけだから子どもは言わない。言えない環境がそろっている学校では、主体性をなくしてだんだんと自分の意見や考えを持たなくなるので扱いやすい子にはなるかもしれないが、それが本当に目指す子どもの姿なのか?と親も考えることが大切だと思います。また、学校の体罰に関するアンケートでは、肉体的な暴力に限定している印象があり、このようなことは傷つくし怖いけれど、体罰ではないかも?と子どもとしては迷うので、本来ならアンケート自体も見直しが必要だと個人的には感じています。
調査の中で聴かれた子どもたちの声
〈不登校の子どもたちが学校で辛かったこと〉
・給食食べる早さ、足の速さ、テストの点数、全部競ってて辛かった
・先生がこわい、大きい声で固まってしまう
・時間に縛られてやることばかりで、全然自由じゃない
・好きなことも得意なことも違うのに、みんな同じ型にはめようとする
・他の子が怒られているのをみると、自分は怒られていないけどすごく怖かった
子どもは未熟で指導が必要な存在だと思い、厳しくしつけなければと思いがちですが、それによって、人として当たり前にある人権や尊厳を傷つけてはいないだろうか?学校こそ子どもが人権感覚を学ぶ場にふさわしい環境であってほしいと願います。
子どもの声から学校を考えるには
学校から子どもたちが消えてしまう前に、毎日安心で楽しみになるような学校にするにはどうしたらいいのでしょうか?
以下は、長野県PTA新聞に掲載されていた、県内の小中学生にアンケートした「こんな学校ならいいな♬」の子どもの意見です。
・宿題をなくす
・スマホOK
・お昼寝できる
・給食をビュッフェにする
・持ち物自由にする
給食以外は、すぐにできそうだなと思うことばかりですが、家でも学校でもほとんど理由も聴かずに批判されたり却下されるとぼやいている子どもの声を耳にします。「大人は、意見は聞くけど聞くだけじゃん!」と子どもは言います。「そう思ってるんだね」と一旦受け止められるだけで、子どもたちにとって学校が安心できる場所になるんじゃないかな?と思います。その為には、まず大人である私たちがただ聴いてもらうという体験が必要不可欠ですが、そういう場所は大人にもないんです。先生や親に相談できないという子どもの背景には、大人の世界が垣間見えてきます。 今、学校に行っている子どもたちの中にも声は出さずとも辛さを抱えている子がいます。地続きで不登校の子どもたちがいるという視点を持ち、一つ一つの意見の奥にある「子どもたちの願い」を丁寧に見ていくことで、未来の学校像が浮かび上がってくる感じがします。
2024年度は地域の小中校長先生方と不登校・行き渋りの子を持つ親との対話会を実施しました。親も校長先生も子どもや教育への思い、不安や困りごとを話し聴き合うことで、立場は違えど子を思う気持ちでつながれるようなあたたかな場になり、お互いに有意義な時間を持つことを意図しています。3月には次年度に向けて「明日も行きたくなる学校づくり」をテーマに対話会を実施します。(子どもの意見も入れる工夫を考え中!)自分の子どもが義務教育を終えたとしても、その先に続く全ての子どもたちにとって、そして先生方にとって学校がハッピーな場所になって欲しい!
たくさんのチカラを集めて実現に向けて活動を続けられたらと願っています。